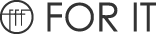先週、熊本の阿蘇山に行ってきました。
阿蘇山は「山」という名前がついていますが、実は一つの山ではなく、巨大な「カルデラ」と呼ばれるくぼみの中にできた火山です。
5つの山が連なっていて、その広さはなんと東京23区がすっぽり入るほどで約9万年前の大噴火によってできたといわれています。
今でも火口からは煙やガスが出ていて、まさに“生きている火山”でした。
実際に火口の近くまで行くと、目の前に広がる巨大な穴からモクモクと煙が立ち上り、硫黄のようなガスの匂いがして、思わず咳き込むほどでした。
見学中には「ガスの濃度が上がってきたので避難してください」というアナウンスも流れ、自然の力の大きさと恐ろしさを肌で感じました。
私自身見に行くまでは火山なので煙がでてるくらいしか前知識なかったので調べると、日本にはこのような活火山が111個もあり、世界の活火山の約7%が日本にあるそうです。
国の面積から考えるととても多く、それだけ日本が火山国だということを実感しました。
一方で、私たちが住む近畿や四国にはほとんど活火山がありません。
その理由は、地下のマグマが出る前に、水分やガスが“温泉”として地表に出てしまうからだそうです。
つまり「火山の代わりに温泉がある地域」なのです。
同じ温泉でも、阿蘇や大分の別府のように火山の熱で温められた“火山性温泉”と、有馬や白浜のようにプレートの圧力でできた“非火山性温泉”があると知り、同じ温泉でも出来方が違うことにとても面白いと思いました。
熊本では地震や津波に加えて火山にも備えて暮らしている人が多く、地域によって自然の脅威が違うのだと感じました。
私自身も地震があった直後は防災グッズをそろえたりしますが、時間がたつとその意識が薄れてしまいます。
今回の阿蘇の体験を通して、「知ること」「学ぶこと」こそが自分の命を守る第一歩だと改めて感じました。
以上です。